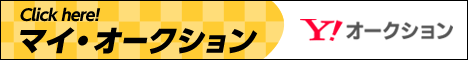| 写真集・近代日本を支えた人々・井関盛艮旧蔵コレクション/当時の写真は歴史的に貴重なばかりでなく日本の風俗の記録としてもまた貴重なもの
平成3年 107P 部数は少なそうです。資料用にもいかがでしょうか。
はじめに
今やシャッターを押すだけでピントから愛出時間まで自動的にカメラが行い,誰もか手早く簡単に写せるようになった「写真」。この写真の技術がわが国に伝えられたのは 永元年(1848)のことといわれています。当時の写真は,銀板写真と呼はれ,撮影に数分を要し、写す方も写される方も苦労の連続で、また経費的にも高く,広く一般に普及
するには至りませんでした。写真が急速に広まったのは、安政年間(1854~1853) ころに,露出時間が5~15秒と短く、何枚でも焼き増しのできる湿板写真が伝えられてからのことでした。
文久2年(1862). 長崎で上野彦馬が間近で下岡蓮杖が我が国で初めての職業写真師として開業して以来,各地で多くの写真師が生れ,数多くの写真が写されました。ちょうど幕末から明治維新という、我が国の歴史のなかでも最大級の変換が行わ れた時期だけに,当時の写真は歴史的に貴重なばかりでなく,日本の風俗の記録としても また貴重なものといえます。本書の写真はちょうどこのころから明治の中ころにかけて 写されたものです。
本書の写真の旧蔵者である「井関盛艮」は,一般的にはよく知られた人物ではありませ んが,伊豫宇和島藩の出身で、明治新政府においては,伊藤博文や大隈重信などとともに 中央で安職を務めた人物です。明治2年からは,地方行政に身を投じ,わが国初の日刊新 聞「横浜毎日新聞」を発刊するなど新時代の施政をしき,また引退後は実業界でも活躍し ました。本書の写真は,現在のブロマイドにあたるものも多く含まれていますが,そのほ かに井関盛艮が中央・地方の行政にあたっていた時期に,何らかのかかわりをもった人々 が名刺代わりに手渡したと思われるものも多数あります。そこに写された人々は,激動の 幕末・維新を生き,そしてわが国の近代化という大舞台で,主役となり,脇役となって活 躍し,あるいは裏方となってそれらを支え、ともに大きな役割を演じてきた人々であり,いわは歴史を作り,動かしてきた人々なのです。近代日本を支えた人々の肖像は,現代の私たちに当時を語りかけているようです。
このたび,本写真集を刊行するにあたり,九州産業大学教授小沢健志氏に監修をお願い いたすとともに王稿を賜り,また元東京大学教授小西四郎氏には王稿を賜りました。さら に資料の提供等多くの方々並びに諸機関にも御協力をいただきました。篤く御礼申し上げ ます。そして何にも増して,本写真を御寄贈いただいた井関家の方々に対し,深く感謝の 意を表するとともに,本書がわが国近代黎明期の歴史・文化の理解の一助となることを願 うものです。
平成3年3月
東京都港区教育委員会
井関盛艮
没年:明治23.2.11(1890)
生年:天保4.4.21(1833.6.8)
幕末明治期の官僚,日本最初の日刊新聞『横浜毎日新聞』の発行者。宇和島藩(愛媛県)藩士で通称斎右衛門。藩命で長崎に赴き坂本竜馬や本木昌造らを知り,海外事情に通じた。維新後は明治政府の外務大丞となり,諸国との修好条約締結に当たった。明治3(1870)年神奈川県知事のとき活版所を開き,子安峻と共に『横浜毎日新聞』第1号を発行した。宇和島,名古屋,島根などの権県令,県令を歴任,退官後は実業家として東京~八王子間の鉄道敷設に尽力した。幕末時には宇和島藩士で最も重要な人物と,アーネスト・サトウに評価された。
お探しの方、お好きな方いかがでしょうか。
中古品ですので傷・黄ばみ・破れ・折れ等経年の汚れはあります。表紙小傷、小汚れ、ややツカレ。ページ小黄ばみ。ご理解の上、ご入札ください。もちろん読む分には問題ありません。460053 |