








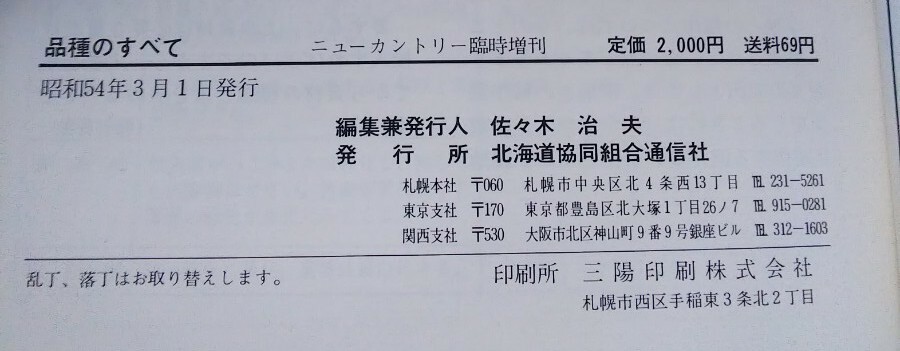
固定種 インゲン 長鶉菜豆 種子 約8粒 クリアパック小分け
60円
画像1右下のクリアパック入り種子の出品です
(種子袋、説明書などは添付しておりませんのでご注意下さい。)
発送は第4種郵便です(リーズナブルな代わりに時間がかかる場合があります)
出品中の他の種子と同梱可能です。
本年度アカヲ種苗さんより購入の物です。
1袋20ml (今回は数えて26粒)で200円でした。
購入後は冷蔵庫にて保管していました。
出品物は約8粒入り 60円
品種名 長鶉菜豆
北海道では以下の品種が長うずら豆として、過去に一定の規模で取り扱われていて、
何れかの系統に由来しているのではないかと思われます。
(北海道での奨励品種とされず、大規模栽培されかった系統の可能性もあります)
※乾燥豆は銘柄という扱い方があり、現在でも豆の外見、調理性質がほぼ同じであれば、違う品種であっても同じ銘柄名を名乗れる様です。
余談ですが、現在乾燥豆として流通している長うずら豆は2005年に育成された 福うずら の可能性が高そうです。
●中長鶉
詳細不明の在来種
●常富長鶉
昭和14年1939年優良品種登録
河西郡 川西村 常富氏 選抜
●菊地長鶉
昭和14年1939年優良品種登録
中川郡 幕別村 菊地氏 選抜
●手無長鶉
昭和14年1939年優良品種登録
河東郡 上士幌村 安村氏 選抜
※名前から推測すると、つるなし又は半つる性
●改良中長
昭和22年1947年 河東郡 音更町 在来の中長鶉から国分氏が選抜、上士幌町を中心に普及。
更に昭和28年1953年、上士幌の下村氏が選抜。
昭和36年1961年優良品種登録。
半つる性 100cm内外
※昭和54年の時点で栽培がほぼ無い
●福粒中長
昭和35年1960年十勝農試にて大正金時×中長鶉(上士幌 産)で交配。
以後固定をはかる。
昭和47年1972年に優良品種登録
半つる性 100cm内外
現在日本のスーパーなどで普及している、一般的な野菜も多くは(茄子、瓜、南瓜、菜っ葉類、大根、かぶ等を除き)
多くが明治~大正、昭和初期に海外から導入された物の様ですが、
特にインゲンは現在和名で残っている品種も大半が明治以降に導入され改名された物の様です。
原名が判れば更に、品種のルーツを辿る事が出来るのですが、長鶉豆に関しては導入後に土着し原名が記録されないまま、改名後の名前のみが残る形となってしまった様です。
画像5~10
参考書籍からの抜粋(情報共有用)
参考書籍
「品種のすべて」
北海道共同組合通信刊/ニューカントリー編集部編/監修 斉藤 正隆 長内 俊一
昭和54年(1979年) 3月1日 発行
ニューカントリー増刊









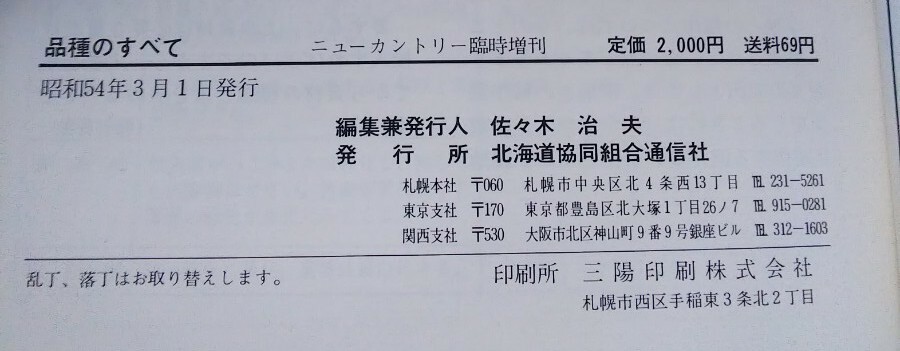 固定種 インゲン 長鶉菜豆 種子 約8粒 クリアパック小分け
固定種 インゲン 長鶉菜豆 種子 約8粒 クリアパック小分け