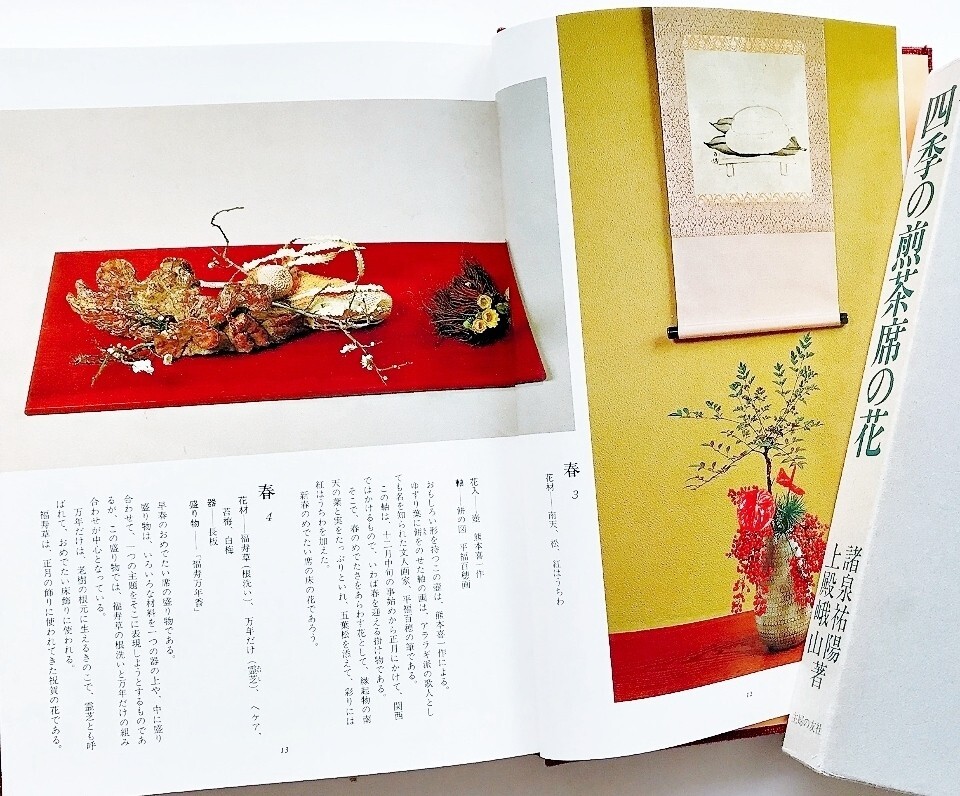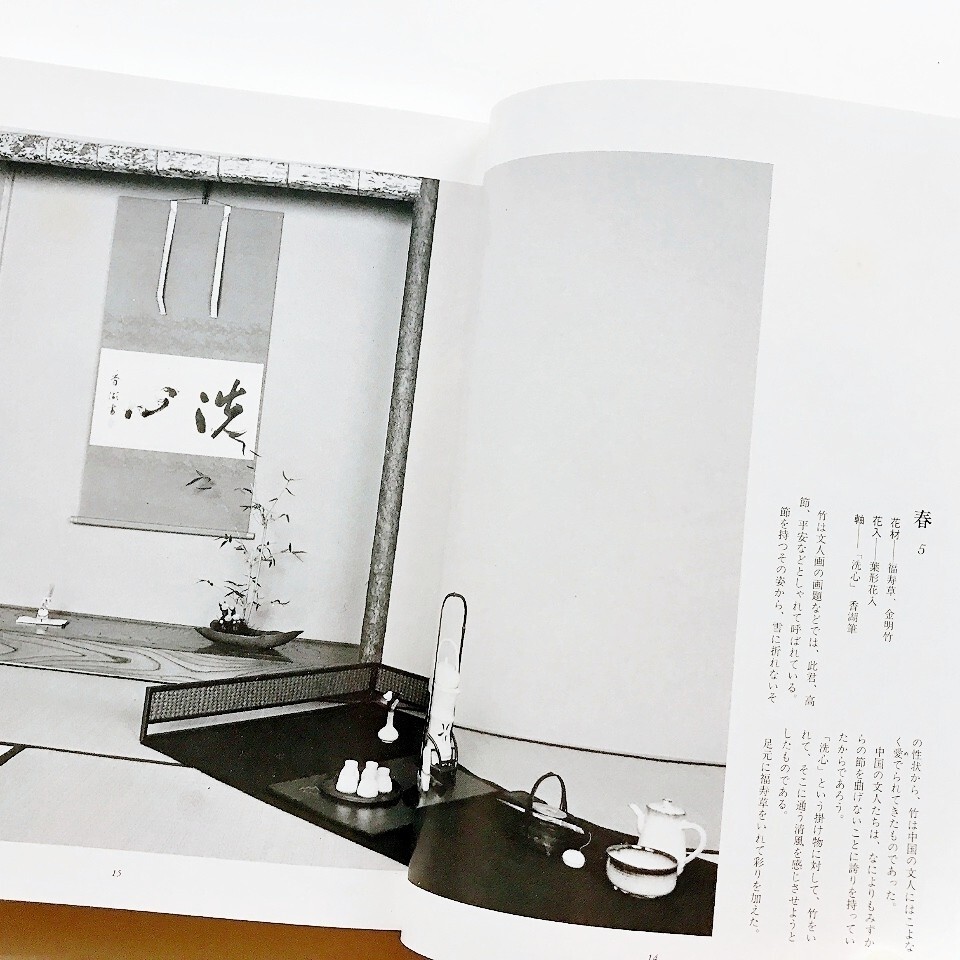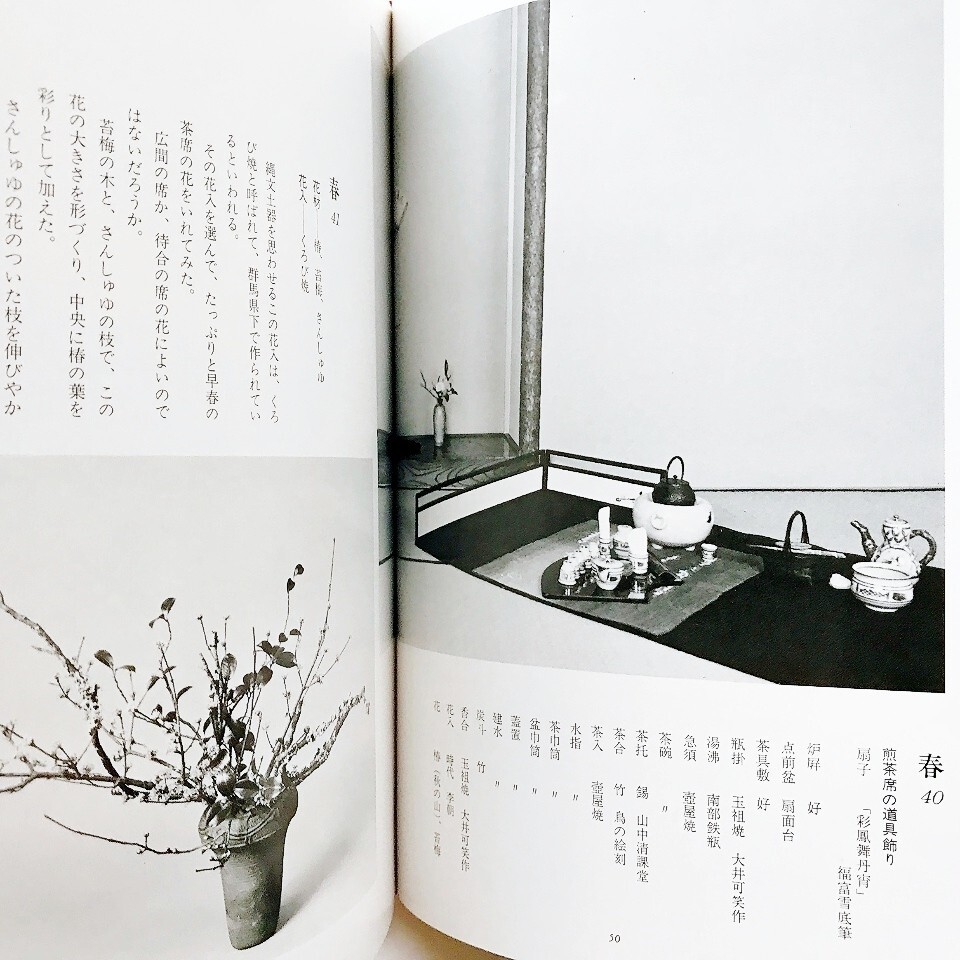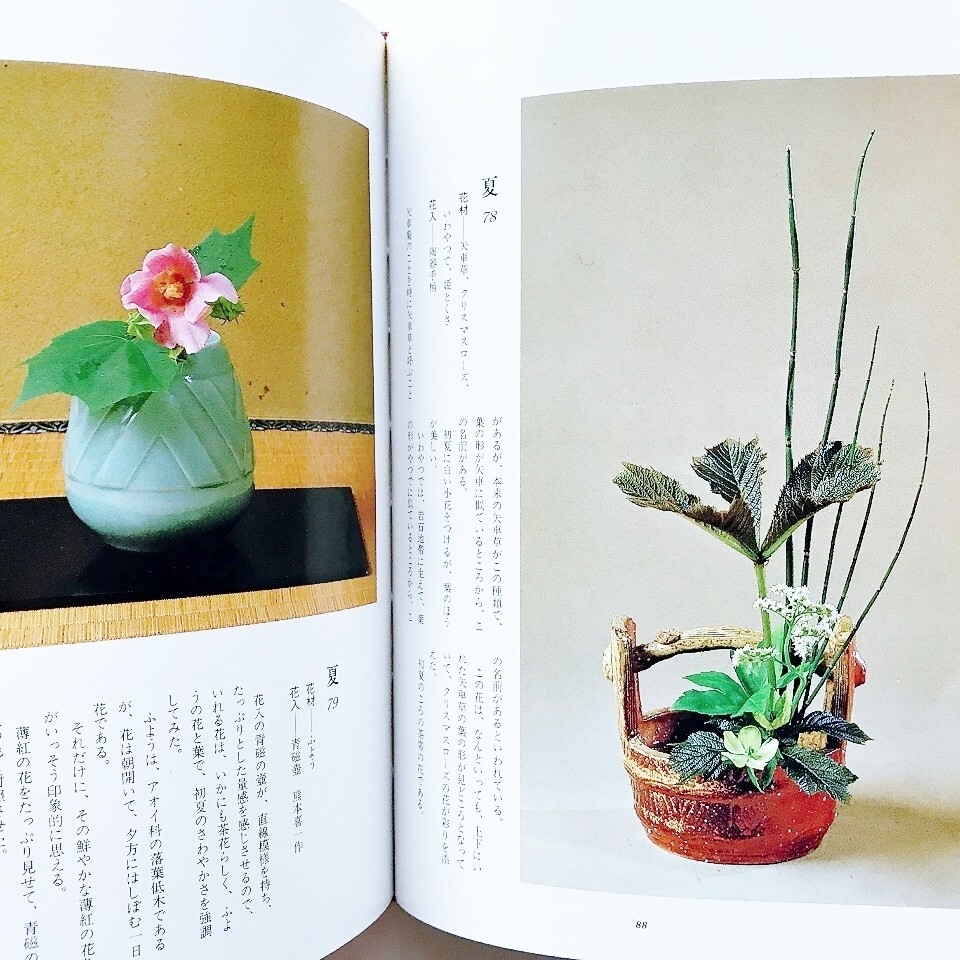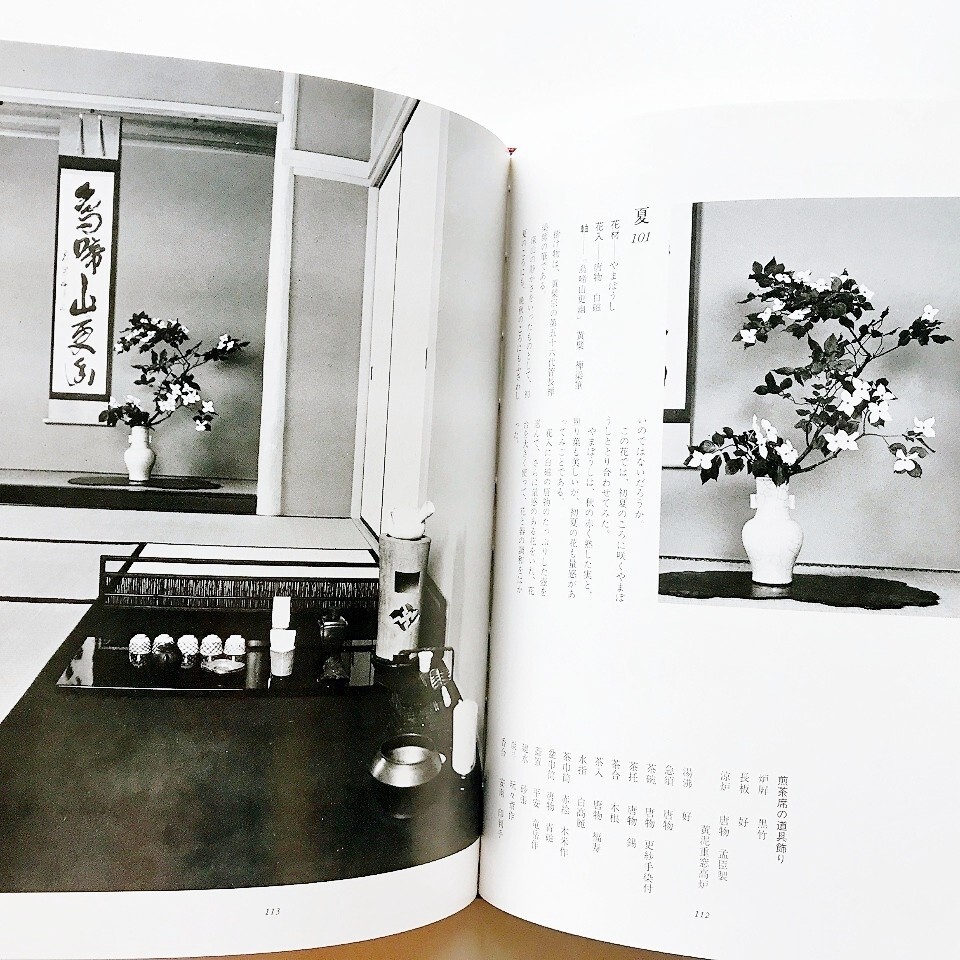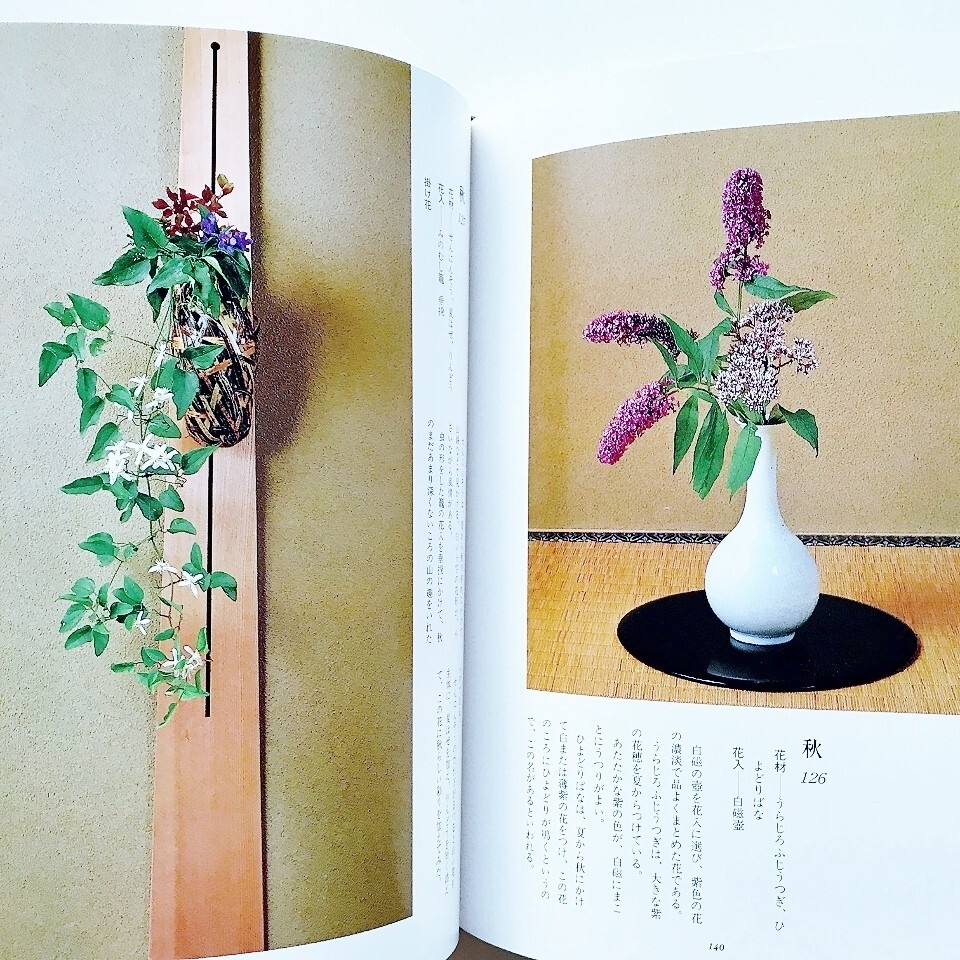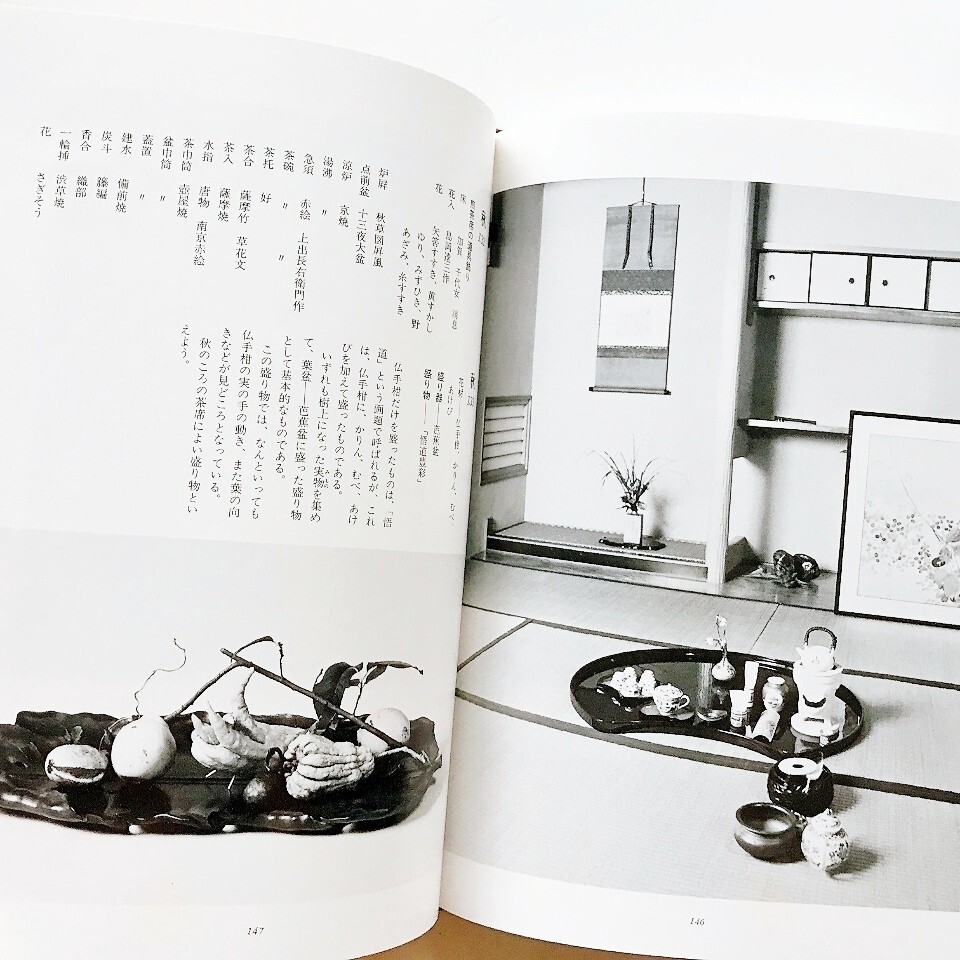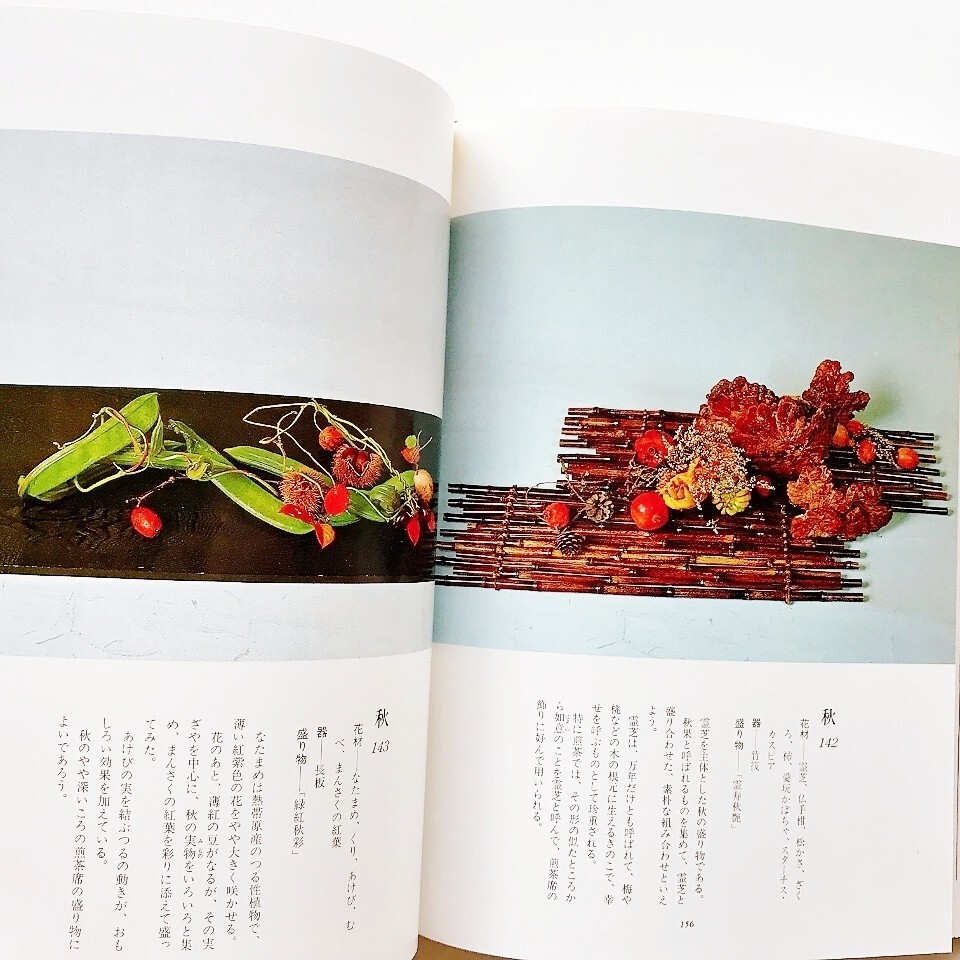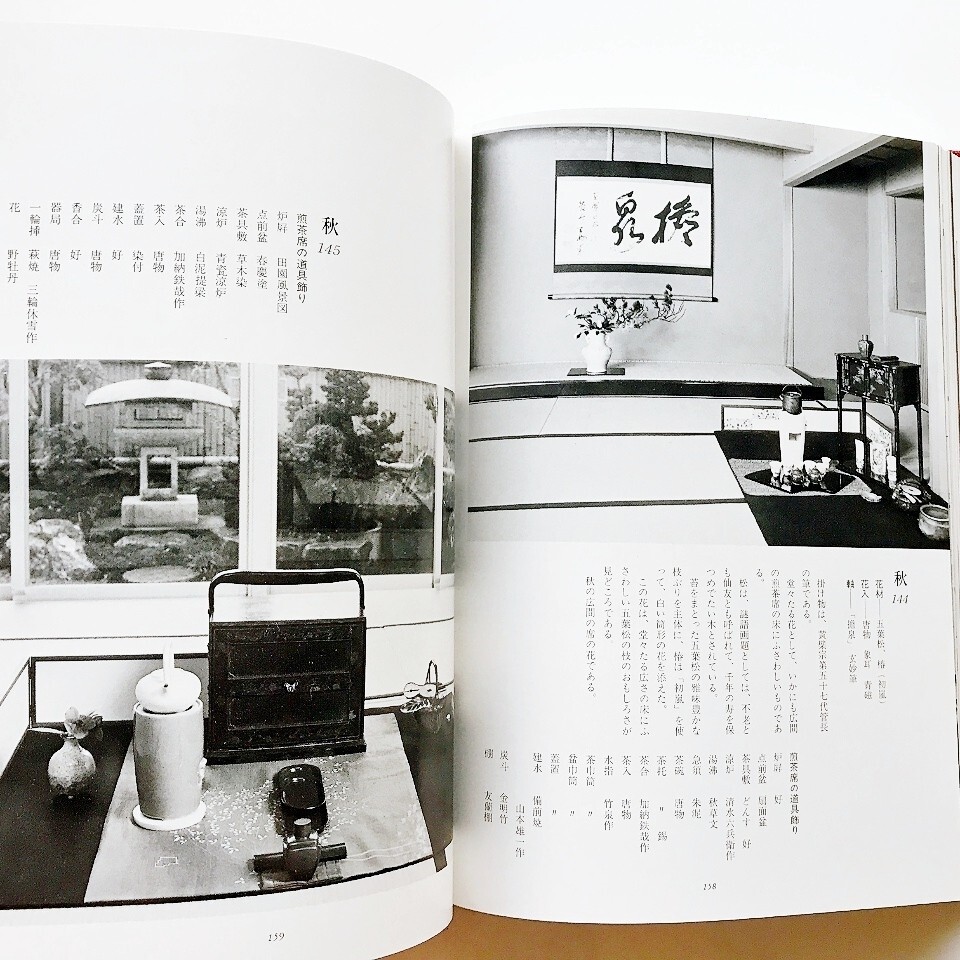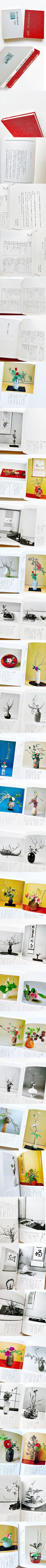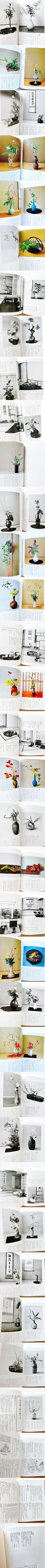絶版希少本 四季の煎茶席の花 煎茶道 専正池坊 日本礼道小笠原流 煎茶道具 盛物 煎茶席 道具飾り 生け花
諸泉祐陽 上殿峨山 著
207ページ
主婦の友社
1982年初版
約26.8 x 19.4 x 2.8 cm
函入 金箔押し布張り上製本
カラー・モノクロ マットコート紙
※絶版
煎茶席の趣向をきめ、それをあらわす大切な飾り、煎茶席の花や盛り物(盛物)を約180余点、季節ごとに分けて収載。
花材、花入、盛物名(盛り物の画題)、盛り器、軸もあわせて、豊富な写真と解説を網羅。
煎茶席の道具飾りには使用した道具類(扇子、炉塀、手前盆、瓶掛、湯沸、急須、茶碗、茶托、茶合、茶入、水指、蓋置、炭斗、建水、香合、茶巾筒、涼炉、銀瓶ほか)
も掲載し、煎茶席での正式な取り合わせ、掛け物との位置関係、置きあわせの全体のバランスなど、
専正池坊 日本礼道小笠原流家元自らがそのノウハウを惜しみなく公開した、非常に有用な資料本・テキスト・教本です。
特に、盛り物の画題、飾り方などについては類書も少なく、貴重な一冊。
【はじめに より】
煎茶席へお客が入ってきて、まず拝見するのが、床の掛け物です。
そして次に、床に飾られている花や花入、あるいは盛り物を拝見します。
煎茶席に飾られる花や盛り物は、それほどに尊ばれているのです。
花や盛り物は、煎茶席に季節を反映させるものです。
季節の花を選び、その時季のものを盛ってこそ、煎茶席に趣が加わります。
売茶翁高遊外が、竹林や松樹のもとで、茶を烹て、行き交う人々に「ただよりは負け申さず」と、茶を売ったとき。
そこには、京都の街なかとはいえ、大自然の空があり、風が吹いておりました。
鴨川のほとりの翁の茶亭、通仙亭でさえ、窓の外には、竹林を渡ってくる風がありました。
今日、私たちの身の回りには、自然は乏しく、季節を知らせてくれる花を見る機会もまた、少なくなりつつあります。
こういうときに、亭主が一碗のお茶をおいしく供し、お客がそれを味わっていただく煎茶の茶席に、季節を語る花や盛り物を飾る意義は、非常に大きなものがあると思います。
まして、その花や盛物は、煎茶席の趣向をきめ、それをあらわすたいせつな飾りなのですから。
この本では、そうした煎茶席の花や盛り物を約百八十余点、季節ごとに分けて収載してあります。
ただ大自然の中で、花はそのおのずからなる季節に咲いて、その時を春といったり、夏と呼んだりしています。
そこで「春」「夏」「秋」「冬」と一応の分類はしてありますが、それはあくまでも目安までのことで、「春から夏へ」と「秋から冬へ」とに分けてごらんいただきたいと思います。
諸泉祐陽
上殿峨山
【著者略歴】
諸泉祐陽
昭和二年 北海道旭川市に生まれる。
昭和二十二年 神戸女学院専門学校英語科を卒業する。
昭和二十三年 二代家元諸泉祐正と結婚し、初代祐道より煎茶道の教導を受ける。
昭和四十年~四十五年 英国に滞在する。
昭和四十七年 専正池坊ならびに日本礼道小笠原流三代家元を継承する。
著書 「日本礼道小笠原流煎茶」(上下主婦の友社刊)、「花とブラスラビング」(毎日新聞社刊)、「四季小品花」(八坂書房刊)ほか
上殿峨山
明治四十三年 山口県田布施町に生まれる。
昭和六年 専正池坊と小笠原流に入門し、川口雲泉師に指導を受ける。
昭和二十二年 中国より帰還し、いけばなと煎茶活動に復帰する。
昭和二十三年 専正池坊ならびに小笠原流家元指導部に入る。
現在専正池坊家元指導部長ならびに、日本礼道小笠原流家元指導部長。
【主な目次 一部紹介】
春から夏へ
春
松、ばら
水仙、若松
南天、松、紅はうちわ
福寿草(根洗い)、万年だけ(霊芝)、ヘケア、
苔梅、白梅
東洋蘭の葉、福寿草(根洗い)、葉牡丹(紅、白)、石福寿草、千両、根引き松
紅梅、さんしゅゆ、やぶこうじ
寒あやめ、ろうばい
房咲き水仙、エリカ
ろうばい、紅椿(太郎冠者)
紅梅ろうばい
煎茶席の道具飾り
ほか
夏
てっせん、白あざみ
あやめ、紅しだ
あじさい、ほたるぶくろ
黒松、牡丹、いたやかえで
牡丹
てんなんしょう、破れがさ、姫ぎばうし、おだまき
みやまはんしょうづる
矢車草、クリスマスローズ、いわやつで、姫とくさ
黄そけい、おおでまりの葉
煎茶席の道具飾り
ほか
秋から冬へ
秋
仏手柑、かりん、むべ、あけび
黄中菊、おとこえし、じゅずだま
まゆみの実、山とりかぶと
煎茶席の道具飾り
野ぶどう(るりたま)、山とりかぶと
大文字草、まんさくの紅葉
吉祥草
ざくろの実、やまじのほととぎす
霊芝、仏手柑、松かさ、ざくろ、柿、愛玩かぼちや、スターチス・カスピア
なたまめ、くり、あけび、むべ、まんさくの紅葉
五葉松.椿(初嵐)
煎茶席の道具飾り
煎茶席の道具飾り
仏手柑、柿、ざくろ、むべ、やつでの花、五葉松
ほか
冬
寒ぼけ
東洋蘭
椿(西王母)
椿(山椿)、松
まんさく、百両(からたちばな)
陪(初嵐)
実ほおずき(冬さんご)、黄すかしゆり
しだ(冬のはなわらび)、寒あやめ
さんしゅゆ、やぶこうじ
ほか
花や盛り物の飾り方
煎茶席の花について 煎茶の花/文人趣味の花 文人華
煎茶席に花を飾る場所は 「青湾茶会図録」天・地・人に収載の席/花を飾る場所を考えてみると
床の間に花を飾る 本勝手の席と逆勝手の床/掛け物との関係
床脇や書院に花を飾る
点前座に花を飾る
花入の選び方
敷板の選び方
盛り物について 盛り物のための文人画画題・花材26種を紹介 四君子、百事如意、春風六客、不老富貴、不老万年、百寿大吉、ほか
★状態★
1982年初版の古い本です。
外観は通常保管によるスレくすみ・経年並やけスレなどがある程度、奥付など余白部分に経年しみ。
カラー写真図版良好、本文は経年並のうすヤケ程度で目立った書込み・線引無し、
問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)