【本】希少図録本 ガンダーラパキスタン仏教美術写真解説論文タキシラ門外不出の釈迦苦行像片岩仏頭菩薩立像ガンダーラ仏像神像仏塔皿140点 收藏
一口价: 7800 (合 386.10 人民币)
拍卖号:x1196144421
开始时间:10/27/2025 22:03:39
个 数:1
结束时间:10/28/2025 21:03:38
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0










140点フルカラー掲載/ギリシャ・ローマ影響の仏教美術 名宝集成
【本の出品です】画像の後に詳細な商品説明を掲載しております。必ず最後までご確認ください。
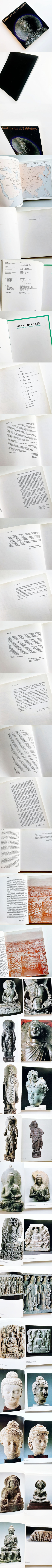
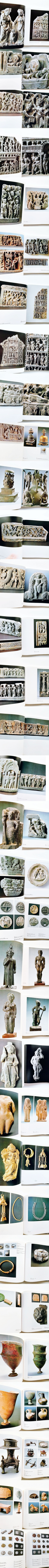
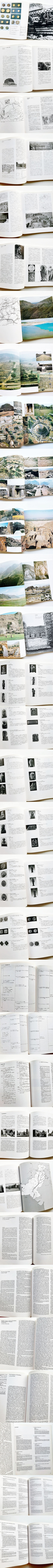
NHKガンダーラ美術取材班による現地取材、京都大学名誉教授・樋口隆康監修。
1984年、日本放送協会発行。全242ページ、25.5×21.5cm、作品図版は全点フルカラー、解説図版モノクロ多数収録の図録本。
本書は、ギリシャ・シリア・ペルシャ・インドの美術様式が融合し、仏教美術の源流とされるガンダーラ美術の至宝を紹介した展覧会公式図録。パキスタン文化省が選定した、同国を代表する140点の門外不出名品を掲載しています。カラチ国立博物館、タキシラ考古博物館、スワート考古博物館、ラホール博物館、ペシャワル博物館、ディール博物館所蔵品より厳選。
内容は、ギリシャ・ローマ文化の影響を色濃く残す酒宴や建築装飾のレリーフ15点、仏陀の生涯を刻んだ仏伝レリーフ21点、寺院遺跡出土の典型的なガンダーラ仏22点、古代コイン25点(金・銀・銅)、化粧皿9点、神像9点、装身具17点、生活用具22点など多彩。特に、世界的至宝・門外不出の「釈迦苦行像」は同国が誇る現存唯一級の傑作で、特別の計らいにより日本初公開された歴史的展示です。
掲載写真は鮮明かつ迫力があり、作品の細部や質感まで伝える高精細印刷。加えて、全作品に詳細な解説、現地遺跡・発掘風景の写真、関連年表や論文を収録。オークションにも出ない、研究資料としても極めて価値の高い一冊です。
NHK ガンダーラ美術取材班 取材
樋口隆康(京都大学名誉教授) 監修
日本放送協会 発行
1984年
242ページ
25.5x21.5x1.5cm
作品図版フルカラー
解説図版モノクロ図版多数
※絶版
ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術の源として有名な、
ガンダーラ美術の至宝を展観した展覧会の会場限定販売公式図録本。
パキスタン国内のカラチ国立博物館、タキシラ考古博物館、スワート考古博物館、ラホール博物館、ペシャワル博物館、ディール博物館から、パキスタン文化省が選定した作品140点が紹介された。内訳は、ギリシャ・ローマ文化の影響をそのまま表現した酒宴のシーンや建築装飾のレリーフ15点、仏陀の生涯を刻した仏伝レリーフ等仏教的な彫刻21点、同国が世界に誇る門外不出の名宝「釈迦苦行像」をはじめ仏教寺院遺跡から出土した典型的なガンダーラ仏22点、さらには都市遺跡から出土した諸民族交流のあとを立証する古代コイン25点(金貨・銀貨・銅貨)、化粧皿9点、神像9点、装身具17点、生活用具等22点・遺跡や現地のフルカラー写真図版に加えて、全作品の詳細な解説、モノクロ写真図版・図解と論文・論考テキスト、関連年表や資料など内容充実の、今となっては大変貴重な資料本。
このたび、パキスタン回教共和国政府のご協力により、仏像彫刻の世界的至宝といわれる釈迦苦行隙を中心に、「パキスタン・ガンダーラ美術展」を東京・大阪・福岡の3都市で開催する迎びとなりましたことは、まことに喜びにたえません。
およそ二千年の昔、シルクロードの要地ガンダーラ地方で、西方の造形美術と東方の仏教文化が出会い、相互に融け合って仏像は誕生したといわれます。こうした仏像彫刻を中心にすぐれたガンダーラの文化遺産をご覧いただくことは、日本仏教美術の源流をさぐるという意味からも、また日本とパキスタンの古いつながりを知るという意味からも、きわめて意義の深いものと信じます。
今回展観される作品は、寺院遺跡出土の仏像、仏伝や建築装飾の浮き彫り、それに都市遺跡出土の工芸品、貨幣など140点で、ガンダーラ美術の全容と、その歴史的背景をご理解いただけるようパキスタン国内6つの博物館から選び出されました。
わけても釈迦苦行像は、現在門外不出とされている貴重な作品ですが、昨年7月、国賓として訪日されたジアウル・ハク大統領閣下の特別のご好意で日本への出品が決定されたものであります。
ユーラシア大陸の東と西、南と北をつなぐガンダーラ。今からほぼ2000年前に栄え、 “仏像”を生み出した古代の国。東西文明の出会いが作り上げたその仏像は、「ギリシア人を父とし、仏教徒を母とする」と言われます。初期仏教の伝統から逃れて、仏像が刻まれるまでには、いったいどんなドラマがあったのか。
カメラは、まず初期仏教美術とストゥーパ礼拝の頃を捉えます。マニキャーラの大塔、シャンカルダルの大塔、そして仏陀の遺骨を納めたといわれる “舎利”容器。それらの中に、仏像のない時代を読み取ります。そして次にカメラは、ガンダーラ文化の一大中心地、タキシラの都市遺跡を訪れます。
東西の文明が混ざりあい、互いに高めあいながら生み出された美術品の数々。そこに、仏像誕生までの経緯が映しだされます。最初期の仏像では、群衆の中の一人として表されていた仏陀が、どのように超人化され、やがて単独の礼拝対象となっていったのか。
東のインド文化と西のヘレニズム・ ローマ文化の出会い・・・・・・。その融合が生み出した美を、如来像・菩薩像の中に見出していきます。また、石像に代わってガンダーラ美術後期の主流となったストゥッコ像にもスポットを当て、その優しげな美しさを解説。続いて、ガンダーラ美術のリアリズムを極限にまで押し進めたと言われる“釈迦苦行像”に話を展開していきます。 仏像のふるさと、ガンダーラ。仏教美術最大の革新をなしえた、この古代の国が、今新たに蘇ります。
主な収録作品―――釈迦苦行像/舎利容器/立像仏頭版《三宝標の礼拝/ハルポクラテス/海馬を取す男/托胎霊夢/誕生,出家決意・出城/涅槃/腕輪 豊饒の友 ほか
ガンダーラは、現在のパキスタン北部に位置するペシャワールを中心とした地方の古い地名で、美術史的には隣接するタキシラやスワートをふくめて東西100 キロメートル、南北80キロメートルに及ぶ地域をさす。この地方は、ヨーロッパや西アジア、中央アジア、中国からインドへ入るシルクロードのなかでも特に重要な地点で、B.C.4世紀のアレキサンダー大王の東征以来、多くの王朝が興亡をくりかえしているが、ガンダーラがとりわけ栄えたのは2~5世紀にかけて当地を支配したクシャーン王朝の時代で、この折り興隆したのが、いわゆるガンダーラ美術である。
ガンダーラ美術は、東西文化の交流によって生まれた西欧的な要素の濃い美術で、インド亜大陸において初めて仏像を現世にもたらしてこれを定型化し、仏像中心の美術を展開した点が特筆される。本来、インド・アーリアン民族のあいだでは、涅槃そのものを形のないものとして考え、仏像不表現の態度が守られていた。これに対し、人体を彫刻的に造形化する伝統のもとに育ったギリシア系民族は、不満をいだき、彼らは、最初さりげなく群像の中に仏陀を刻み、次いで仏伝の主人公として典型的に表わすようになり、最終的に仏陀を単独像として表現するという永年にわたる手順をふんで、インド・アーリアン民族のタブーを、ガンダーラの地にあって、打ち崩していったと考えられる。このガンダーラ美術の特色は、やがて広くインド、中央アジア、中国、日本などの仏像表現に大きな影響を及ぼすことになる。
本展では、パキスタン国内のカラチ国立博物館、タキシラ考古博物館、スワート考古博物館、ラホール博物館、ペシャワル博物館、ディール博物館から、パキスタン文化省が選定した作品140点が紹介された。内訳は、ギリシャ・ローマ文化の影響をそのまま表現した酒宴のシーンや建築装飾のレリーフ15点、仏陀の生涯を刻した仏伝レリーフ等仏教的な彫刻21点、同国が世界に誇る名宝「釈迦苦行像」をはじめ仏教寺院遺跡から出土した典型的なガンダーラ仏22点、さらには都市遺跡から出土した諸民族交流のあとを立証するコイン25点、化粧皿9点、神像9点、装身具17点、生活用具等22点で、ガンダーラ美術における仏像出現の発生過程や同美術を育てたクシャーン民族の生活などを知るのに十分な内容となっていた。
なお本展は、NHK教育テレビジョン放送開始25周年を記念して企画され、当館に先だって東京の西武美術館にて開催され、当館閉幕後に福岡市美術館へ巡回した。
ごあいさつ
メッセージ パキスタン回教共和国大統領 ジアウル・ハク
メッセージ パキスタン回教共和国文化大臣 ニアズ・モハマド・アルバブ
序文 京都大学名誉教授 樋口隆康
序文 パキスタン回教共和国文化省次官 マスード・ナビ・ヌール
図版
論考テキスト
ガンダーラの地理と歴史 樋口隆康
都市遺跡タキシラ 田辺勝美
タキシラ・ガンダーラの仏教寺院 桑山正進
ガンダーラの彫刻 宮治昭
作品解説
ガンダーラ関連略年表
主要参考文献
出品博物館紹介
釈迦苦行像 Fasting Buddha
片岩 シクリ出土 3-4世紀頃 84×53cm ラホール博物館
ガンダーラ美術の特徴のーつである、リアリズム(現実主義)表現を極度に押し進めた傑作。シッダールタ太子は悟達を求める多くの遍歴の後、最後に苦行に入る。6年間に及ぶ激しい断食苦行をなしたと仏典は伝えている。ガンダーラの工人は・釈尊のその肉体的苦しみに耐え抜いた神々しいばかりの精神力を表そうとしている。落ち窪んだ眼、骸骨のような痩せこけた体躯のリアルな表現は、観る者に釈尊の精神的苦しみを感じさせる。しかも現実主義から出発しながら、ここにはそれを超えた崇高さがある。一方、衣文は並行線状の様式的な襞で表しており、台座上の吉祥草の装飾的な表現と、台座正面に表された燈火擅と6人の礼拝する比丘の左右相称的な表現とともに、この像に不思議な均衡感を与えている。インド内部では苦行像は知られず、釈尊を歴史的・人格的存在として捉えたガンダーラの工人の現実感覚がよく窺える。(宮治)
仏立像 Standing Buddha
片岩 出土地不詳 2世紀頃 138×46cm ラホール博物館
方形の台座上に立つ仏陀像。釈迦仏であろう。右手は欠失するが、施無畏印をとっていたものと思われる。左手は垂下し、衣端を握っている。無文の頭光、波状の頭髪、彫りの深い若やいだ顔立ちなどガンダーラ仏の特徴がよく窺える。僧衣を通肩にまとい、衣文の襞を深く刻む。左膝頭を透けるように表して、左脚を遊ばせ、右脚に亜心をおいて支脚としている。この表現はグレコ・ローマ彫刻の伝統を継承したもの。台座(7.6 cmx 35 cm)は、コリント式柱頭をもつ付け柱で区画され、そこに舎利器を礼拝する6人の人物(向かって右に3比丘・左に1比丘と2女性)を表す。(宮治)
仏立像 Standing Buddha
片岩 マルダーン地区ダウラト付近の村より出土 2-3世紀頃 126×42cm ペシヤワル博物館
両手を欠損するが、他は保存がよい。頭光に葉状の縁取りをつける。顔は卵形で、瞑想風の穏和な顔立ち・波状の頭髪を頂部で束ね、肉髻とする。白毫を浮彫で表している。通肩にまとった衣文はやや重苦しく、襞の表現は線条的となっている。両足の間、台上に穿たれた穴は賽銭用のものと考えられている。台座の上部は鋸歯文と軒持送りの飾で飾り、前面には5人の供養者(向って右に3人、左に2人)によって合掌、作礼さている禅定の菩薩を表す。両端にコリント式柱頭の付け柱をおく。台座の側面には花文がみえる。(官治)
菩薩頭部 Head of Bodhisattva
片岩 出土地不詳 2世紀頃 38×22cm ラホール博物館
ターバン冠飾をつけた、美しい菩薩の頭部。半眼の瞑想風の眼差しで、口もとに長い髭を生やし、静寂な表情をみせる。眉間の穴には白毫を表すため、もと宝石が嵌められていた。ターバンの冠飾はとりわけ豪華で、周囲にマカラ、トリトーン、ケンタウロスなどで飾り、頂部にナーガ(龍)とナーギニー(龍女)を塵う鷲を大きく表している。これは、永遠の若さと美に輝く美少年ガニュメーデスを、鷲の姿に化したゼウスが天上に攫っていったという、名高いギリシア神話に由来するもの。この主題をガンダーラの仏教徒がどのように再解釈したのか、不明な点が少なくないが、おそらく菩薩の救済的な性格を顕すものであろう。(宮治)
菩薩立像(弥勒?)Standing Bodhisattva (Maitreya?)
片岩 サフリバロール出土 2世紀頃 153×53cm ペシャワル博物館
両手を失うが、頭部・体躯ともよく残るガンダーラの代表的な菩薩像の一つ。頭光は無装飾の大きな円盤で表している。弥勒菩薩に特徴的な束髪式の髪型を示し、頚飾・胸飾・聖紐・臂釧などで豪華に身を飾る。上半身裸形の体躯は、的確な人体構造の把握とモデリングを示し、支脚・遊脚の表現とともに、グレコ・ローマ彫刻の伝統を巧みに摂取している。ドーティー(裳)は、大腿部・脚が透けるように薄めに表すが、襞は煩瑣なまでに抑揚をみせている。足にはサンダルをはく。方形台座の正面に、交脚の菩薩像とその両側に3人ずつの供養者を表している。(宮治)
菩薩立像 Standing Bodhisattva
片岩 ペシャワル出土(?) 3-5 世紀頃 134×50cm カラチ国立博物館
仏鉢とそれを礼拝する4人の供養者を表した台座上に立つ菩薩像。右手を欠するが、左手は腰に当て、肘を張って威厳を示す様子。頭にターバンの冠飾をつけ、頭光にパルティア風の冠帯を翻す。宝石を散りばめた板状の頚飾、向い合う2つの龍頭をつけた胸飾、左肩より右肩と右脇にそれぞれ掛けた2条の飾紐、さらには臂釧と腕釧などで身を飾っている。この菩薩像には王者としての性格が強く顕れている。左肩より左腕に巻いて右前腕部にかけた条帛とドーティー(裳)には、ジグザグ形式の様式的な襞の表現がみられる。(宮治)
仏陀と梵天,帝釈天(梵天勧請)
Buddha、 Brahma and Indra (Brahma and Indra entreat Buddha to preach)
片岩 スワート地方出土 6-7世紀頃 41×42cm スワート博物館
花文で飾られた台座上に結跏趺座して禅定印を結ぶ仏陀。両脇に合掌作礼する梵天と帝釈天を従える。頭上に大きく沙羅の技が垂れ下り、左右上端に供養の天人を表す。釈尊が成道後、自己の悟りを人々に説くのをためらっていたとき、梵天をはじめとする抻々が人々のために説法されんことを要請したという、「梵天勧請」の場面ともみられる。頭髪や衣文に様式化した線条的な表現が著しく、左右相称的な柵図とともに、パルティア美術と共通する特徴が窺える。同時に、まろやかな体躯の表現には中インドの彫響もみられる。スワートからはこのような様式的特徴をもつ一群の彫刻がある。製作年代に関しては2~7世紀にわたる諸説がある。(宮治)
仏頭部 Head of Buddha
ストゥッコ モフラーモラードウ(タキシラ)出土 4-5世紀頃 高さ38cm タキシラ考古博物館
大型の仏頭で、復原すると身長3、4m位の仏立像となろう。頭髪は螺髪で、顔に丸味があり、伏眼勝ちである。鼻と両耳の下端が欠けているが、典型的なストゥッコ仏頭をあらわしている。ガンダーラ美術のうち、後期の作である。(樋口)
仏頭部 Head of Buddha
ストゥッコ スタッコ モフラーモラードウ出土 4-5 世紀頃 高さ18cm カラチ国立博物館
タキシラのモフラーモラードゥ寺の僧院からの発鋼による出土品。保存状態が大層よく、額・眼・瞼・唇・頚筋などに赤の彩色の痕が残る。やや豊満な顔立ちの中に。優しさが漂っている。ストゥッコ像は石彫と異なり、その柔軟な材質のゆえに、微妙な顔の表情が表現しうる。ガンダーラ美術の後期にタキシラとアフガニスタンのハッダにおいて、とりわけストゥッコの造像が好まれた。この仏頭はその代表的な作品の一つ。頭髪はなお波状に表されているが、様式化が著しい。(宮治)
ほか
<仏像>
釈迦苦行像 仏立像 菩薩頭部 菩薩立像(弥勒?) 菩薩立像 仏座像 仏胸像 禅定の仏陀(舎衛城の神変?) 仏陀と菩薩と供養者 仏三尊像 仏陀と梵天・帝釈天(梵天勧請) 仏頭部 菩薩頭部 マトゥラーの仏座像 仏座像 菩薩座像 本生・仏伝 わが子を争う二人の女(マハーウマッガ・ジャータカ) 燃燈仏授記本生と仏伝 托胎霊夢 誕生 仏誕・七歩行 誕生・出家決意・出城 宮廷生活・出家決意 出城とその讃嘆 魔衆の攻撃 三宝の礼拝 仏への布施(ナンダの出家?) スマーガダーの説話 死女が子を産む説話 仏伝5種 涅槃 納棺 ほか
<ストゥーパ>
小型ストゥーパ ストゥーパ形舎利容器 花綱と童子 饗宴 愛の場面 愛の場と僧房 供養者群像 トリトーン 柱形装飾 門口に立つ供養者 兵士と楽人 槍を持つ兵士 アトラス 柱頭 ほか
<化粧皿>
化粧皿 アポロンとダフネー 化粧皿 杯を持つ男女 化粧皿 男女像 化粧皿 騎馬のディオスクーロイ 化粧皿 海馬を馭す男 化粧皿 海獣を馭す女 化粧皿 海馬 化粧皿 死者の饗宴
<神像>
ハルポクラテース(ホールス、ホルス) 豊穣の女神 槍を持つ女神 女神 豊穣の女神 男女像 ほか
<装身具>
耳飾 垂飾 女神像のブローチ 金鎖の頸飾 指輪 印章(玉髄) 腕輪 踝飾 柄鏡 櫛 有角獅子頭飾板
<生活具>
台付杯 四つ口の壺 柄香炉 水差し 香炉 インク壺 馬具 石輪 車輪をつけた馬 象 ほか
<貨幣・古代コイン(金貨・銀貨・銅貨・パンチ刻貨)>
デーメートリオス貨幣 インド・グリーク王国 アポロドトス貨幣 インド・グリーク王国 パンタレオン貨幣 インド・グリーク王国 メナンドロス貨幣 インド・グリーク王国 ストラトーン貨幣 インド・グリーク王国 テレフォス貨幣 インド・グリーク王国 ヘラオス貨幣 クシャン族 マウエス貨幣 サカ=インド・スキタイ族 アゼスⅠ世貨幣 サカ=インド・スキタイ族 アジリセス貨幣 サカ=インド・スキタイ族 ソーテール・ガメス貨幣 クシャン族 クジューラ・カドフィセス貨幣 クシャン族 クジューラ・カドフィセス貨幣 クシャーン朝 カニシュカⅠ世貨幣 クシャーン朝 フヴィシュカ貨幣 クシャーン朝 ヴァース・デーヴァ貨幣 クシャーン朝 カニシュカⅢ世貨幣 クシャーン朝 ホルマズドⅠ世貨幣 クシャノ・ササン朝 キダーラ・クシャン貨幣 ほか
ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術として有名である。開始時期はパルティア治世の紀元前50年-紀元75年とされ、クシャーナ朝治世の1世紀~5世紀にその隆盛を極めた。インドで生まれた仏教は当初、仏陀そのものの偶像を崇拝することを否定していたが、この地でギリシャ文明と出会い、仏像を初めて生み出した。インドをはじめ、中国や日本にも伝わり、また大乗仏教も生まれた。「兜跋毘沙門天像」という頭に鳳凰のついた冠をかぶった像が存在し、毘沙門天の起源がギリシア神話のヘルメース(ローマのメルクリウス)であるという説がある。5世紀にはこの地にエフタルが侵入し、その繁栄は終わりを告げた。
ほか
1984年のとても古い本です。
外観は通常保管によるスレ、開きじわ程度、背表紙中心部に縦じわあり、天小口に経年並ヤケ・しみあり。
P112と113の間の、強い開きグセがあります。
余白部に経年並ヤケしみなどありますが、カラー写真図版良好、目立った書込み・線引無し、
問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)
<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、貴重な一冊です。
古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひよろしくお願いいたします。
■落札後は、迅速なお受取連絡にご協力をお願いいたします。
■中古品につき、経年に伴う変化や保管時のスレ等がある場合がございます。
■掲載写真はできる限り実物に近い色味を再現しておりますが、モニター環境により多少異なる場合がございます。
■絶版・希少本や限定品、出版社で入手困難品は、市場相場に基づいた価格設定を行っております。
■お支払いは「かんたん決済」に対応。決済画面の控えを領収書としてご利用いただけます。
■発送・取引ナビ応答は平日に行います。特別な発送スケジュールがある場合は、自己紹介欄にて事前にご案内しています。
■商品やお取引に関して気になる点がございましたら、評価入力前に取引ナビよりご一報ください。
確認のうえ、誠意をもって対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。
■上記の点をご了承いただいた上で、ご入札くださいますようお願いいたします。

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐