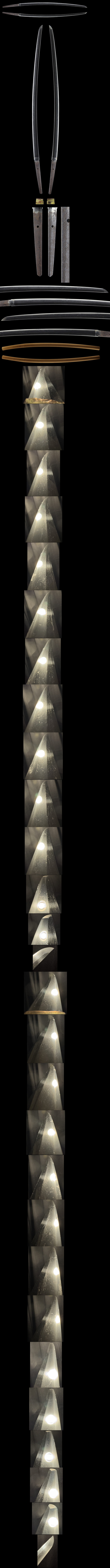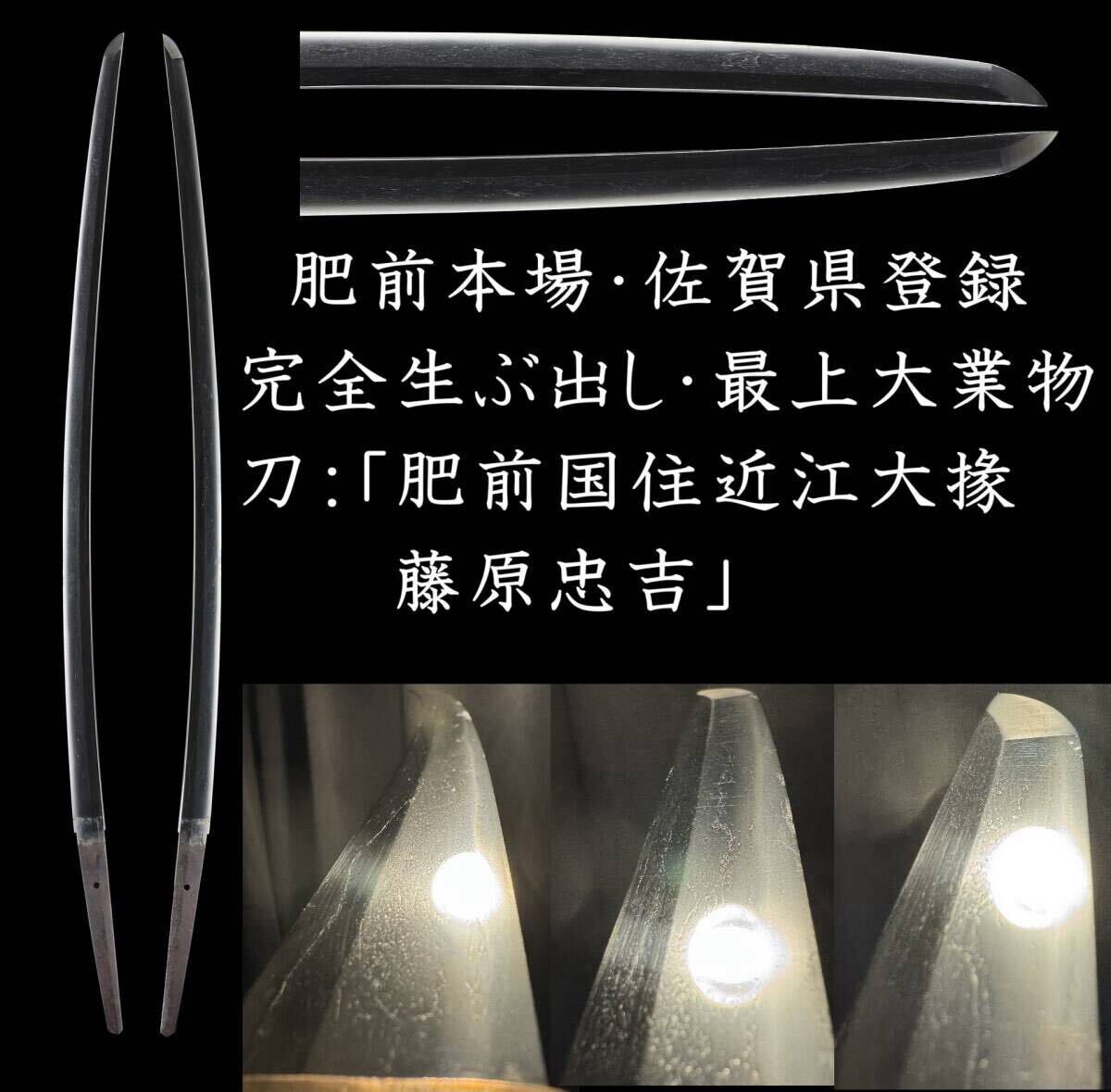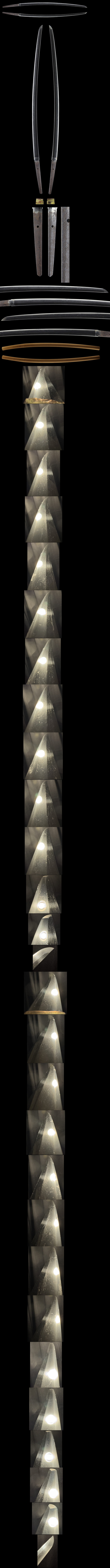重量:鞘を払って約750g
【刀身】
本造り、庵棟、身幅元先の幅開き、反り深くつき、踏ん張りついて、やや小鋒となる
鍛え、小板目肌が精緻によく詰み、処々に肌を交えて流れ、鉄色冴えて、地沸厚くつく
刃紋、直刃、浅く湾れを交え、小沸がよくついて締まりごころとなり、処々ほつれ、食い違え刃入り、砂流しかかる
帽子、直に入り、やや掃きかけて小丸に返る
中茎、生ぶ、先剣形
ハバキ、真鍮二重
【説明】
肥前の名工・近江大掾忠広による、大和伝写しの長寸・2尺4寸8分の傑作刀です。
近江大掾忠広は、肥前刀の開祖である初代・肥前忠吉の子として生まれ、父・忠吉の没後、わずか十九歳で忠吉家を継ぎました。
寛永十八年には、朝廷より「近江大掾」の受領名を賜り、生涯にわたり「忠吉」を名乗ることはありませんでしたが、
実質的には二代目忠吉として、鍋島藩の抱工として数多くの名刀を世に送り出しました。
元禄六年、八十一歳で没するまで多作であり、とりわけ分家筋の河内大掾正広や他の一門の支援を受けたことで、肥前刀の全盛期を築き上げ、
鍋島焼と並ぶ佐賀藩の名産品として名を馳せました。肥前刀の中でも別格の棟梁とされ、その影響は計り知れません。
作風としては、父・忠吉が晩年に好んだ、沸・匂いが深い中直刃に、「肥前の小糠肌」と称される小板目が詰んだ精美な地鉄が一般的ですが、
本作のように、藩侯や重臣の求めに応じて古刀の名作を写したものを、極めて稀に製作することがあり、大変に珍重されています。
本作は、忠広および肥前刀の特徴である小板目肌が顕著に見られますが、刃文は小沸がよくついて締まりごころとなり、
所々に食い違い刃を交え、大肌を交えた地鉄などからも、一見して大和物、おそらくは手掻あたりに範を取った変わり出来の優作であり、
前述のとおり、極めて珍しい特別注文による傑作刀となっています。
それでいて、直刃や地鉄には肥前刀特有の帯状および小糠状の精緻な鍛えが残っており、大変な魅力があります。
長さは異例の2尺4寸8分、反りも通常より深くつき、踏ん張りがあり、やや小鋒となっている刀姿は、
紛れもなく鎌倉時代の太刀を写したものであり、おそらくは太刀拵を佩く身分の、藩侯や佐賀藩分家の当主による注文品と思われます。
本作は、肥前刀の地元・佐賀県で登録されており、長年にわたり地元で大切にされてきたことが窺えます。
実際に所持していたのは、鍋島家にゆかりのある方とのことで、大変な生ぶ出しの刀となります。
研磨はかなり以前に施されたものと推定され、所々に錆や傷、ヒケなどが見受けられますが、刃切れなどの致命的な傷はなく、
現状では未鑑定品ではあるものの、上研磨を施せばさらに鮮やかに大和伝の写しとしての姿が明瞭になり、
極上の刀となることは間違いありません。
肥前刀、なかでも忠吉家による特別注文の変わり出来は、博物館や注文主の子孫などの手に秘蔵されており、
極めて稀にしか市場に出回ることがありません。
肥前刀、そして忠吉家にご関心をお持ちの方には、決して見逃していただきたくない、
資料的にも美術的にも極めて貴重な一振りです。ぜひこの機会をお見逃しなく、お求めください。
【ご注意事項】※入札前には必ずお読みください。入札後は以下へ同意いただけたものとさせていただきます。※
・本商品は委託出品ですので、返品不可、ノークレームノーリターンでお願い申し上げます。
・商品の写真はできるだけ現物に忠実なように撮影していますが、どうしても現物の状態を表現しきれていない場合がございます。
・商品が未鑑定品の場合、商品説明の記述は見解の一つであって鑑定結果等を保証・お約束するものではございません。
・骨董品・中古品であるという事をご理解いただき、過度に神経質な方のご入札は申し訳ありませんがお断りいたします。
・寸法は、専門の器具を使用して採寸している訳では無く、あくまで素人採寸のため誤差はご容赦ください。
・写真を良くご覧の上ご判断いただき、あるいはご質問をいただいた上で責任のあるご入札をお願いいたします。
・終了の当日や終了直前でのご質問には回答できない可能性がございますので、ご質問は時間にゆとりを持ってお願いいたします。
・落札後24時間以内のご連絡、3日以内のご入金、および受取後24時間以内の受取連絡をお願い致します。
・ご連絡ご入金頂けない場合、誠に恐縮ではありますが入札者様都合で落札を取り消させていただく場合もございますのでご注意ください。
・評価が新規の方でご連絡が無い方、および過去の取引にて著しく悪い評価がある方の場合、入札をキャンセルさせていただくことがございます。