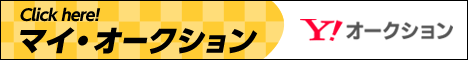| 古文書研究・9冊でまとめてみました。
部数は少なそうです。資料用にもいかがでしょうか。
はじめに
床の間,床脇, 書院等の座敷飾りに代表される日本座敷の空間は,知られ ているように, 日本建築の発達, 推移変遷の歴史の上に成立しているもので す. したがってそこには深い経験と実証に裏付けられた知恵が集積されてい て,そのまま日本建築の特質として語られています。
今日では,たとえば新建材の利用,電動工具の使用, 新構法の導入、建築 技術に携わる人々や施主をとりまく社会経済環境など, 建築に関する話題は 少なくありませんが,現在の木造建築に関していえば,これらによって従来 からの設計、施工技術の本質が揺らぐものとは考えられません.これは素木 造りを基本とする日本家屋が,わが国の気候, 風土に順応した建築で, 古く からわれわれ日本人の日常生活の器として,また,風俗, 習慣, 思想など文 化的な営みの拠り所として永い伝統を保ち、 今日まで守り伝えられてきたか らでもありましょう。
本書は日本家屋の内部造作工事のうち,とくに座敷回りの工法に重点を置 いて解説したものですが,上に述べたような考え方から,いずれの説明に当 たっても従来からの手法を基調として, 現在の工法に関連づけることをつね に心掛けました.
私はかって木造建築の技術に関するいくつかの本を著わしてきましたが, その中でいずれの機会にも思い当たったことは, 木造の技術というものは、 各人による手法の相違、 材料・ 意匠による納め方の相違があって,これが定 法であるといいきれない側面があることでした. 本書でふれなかった技術, 手法なども多々あるかと思いますが, 読者の皆様からご教示, ご叱正を頂け れば幸です.
最後に, 本書の完成に際しては多くの図書を参考にさせていただきました. これらの諸文献の著者の方々をはじめ、 多忙の中、 種々の貴重なお話を聞かせ て下さった先輩諸兄, 並びに私の原稿を督促され, 終始激励して下さった出 版元の富田宏さんに厚くお礼を申し上げます.
H
お探しの方、お好きな方いかがでしょうか。
中古品ですので傷・黄ばみ・破れ・折れ等経年の汚れはあります。表紙小傷、小汚れ。2-3冊ぱらぱらとめくった感じでは、書込み・線引き等見当たりませんが、
見落としあればご容赦ください。ご理解の上、ご入札ください。もちろん読む分には問題ありません。280692S
|